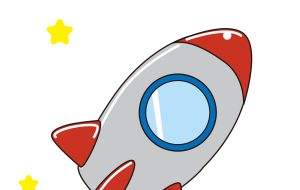レポート
2019/01/31
芸術はすべての壁を 超える出会いの場

「藝大アーツ・スペシャル2018障がいとアーツ」より © 平舘平
2019年になり、いよいよ「2020東京」が間近に迫ってきました。ダイバーシティなスポーツの祭典の開催に向け、芸術分野でも障害のあるアーティストの活躍や、障害のあるなしに関わらず楽しめる催しが増えています。そんな中、東京藝術大学ではいち早く2011年から、芸術を通してすべての人々が交流するイベント「藝大アーツ・スペシャル ~障がいとアーツ~」を開催しています。2018年12月1日、2日に開催された8回目の「障がいとアーツ」をレポートします。

「秋」のイメージを表現したアニメーションがバイオリンの音色に合わせて動く
誰もが楽しめる 聞こえる色 見える音
「藝大アーツ・スペシャル ~障がいとアーツ~」は、芸術を通してすべての人々が交流するというコンセプトどおり、初回から多種多様な障害のある人々が同じ会場で、同じ芸術を享受するための試みに挑戦し続けている。当初は、障害のあるプロのアーティストの演奏を、さまざまな障害のある人たちがともに楽しめるイベントとしてスタート。2015年からは、同大学が文部科学省と科学技術振興機構(JST)による産官学連携プロジェクト「センター・オブ・イノベーション(COI)」の拠点に認定されたことで、科学技術と芸術を融合させた革新的な表現の可能性を追求することも開始。科学技術系の企業と連携し、障害者が芸術に触れる機会を増やすための新しい楽器や補助デバイス(装置)の開発を進めている。

共感覚メディア研究グループ
左からグループリーダーの越田乃梨子さん、桒原寿行さん、東京藝術大学COI拠点リサーチリーダー桐山孝司教授、上平晃代さん、薄羽涼彌さん
今回のメインコンサートは「聞こえる色、見える音」をテーマに、音楽の映像化、音量の視覚化など、さまざまな試みが行われた。プログラムのひとつヴィヴァルディ作曲<四季>より「秋」「冬」は、AI(人工知能)を搭載したシステムによるアニメーション映像付きで演奏された。このプログラムを開発したのは「共感覚メディア研究グループ」とヤマハ株式会社のメンバー。開発当初はすべて人力で生演奏に合わせ操作していたという。「音に合わせてアニメの動きを操作するには、大変な練習と集中力が必要。コンピューターの助けを借りることで、スタートのタイミングなど人間にしかできない操作のみ人力で行うシステムが実現した」とCOI拠点リサーチリーダーの桐山教授。当日の出来をグループリーダーの越田さんは「指揮者の動きや演奏と同じリズムでアニメが動くのを見て、映像自体が演奏しているように感じた。音が聴こえない人にも<四季>という作品の豊かな魅力が届いたならうれしい」と話す。
テクノロジーの サポートで 次は舞台へ

東京藝術大学COI拠点
障がいと表現研究グループ
新井鷗子特任教授
本イベントの総合プロデュース、司会も務めた同大学COI拠点「障がいと表現研究グループ」の新井鷗子特任教授は「さまざまなデバイスの開発により、障害のある人が芸術を鑑賞できるだけでなく自ら演奏することも可能になった」と話す。そのひとつがこの日のプログラムのシュトラウスI世作曲<ラデツキー行進曲>だ。新井特任教授と桐山教授の研究グループとヤマハ株式会社研究開発統括部、筑波大学附属聴覚特別支援学校の共同研究により開発した、音量をリアルタイムで視覚表示するシステムにより、聴覚障害のある5人の子どもたちが一糸乱れぬスネアドラム演奏で、オーケストラとの見事な共演を果たした。
コンサートのエンディングでは、会場の子どもたちが一斉にステージに登り、思い思いの場所で演奏を楽しんだ。大きな太鼓の近くに座る子、バイオリニストの足元にぴったり寄り添う子。「聴覚障害児に音の振動を感じてほしくて始めた試みが、障害の種類や有無を超え毎年の恒例に」と目を細める新井特任教授。「スポーツは障害のあるなしでルールが異なるけれど、音楽は同じ楽器、同じ楽譜、同じステージで演奏し鑑賞できる。芸術は誰もが同じ土壌で楽しめるもの。これからもさまざまな人と人の出会いの場であり続けたい」と、その挑戦はさらに続く。
皆さんも身近な場所で、ちょっと気になる演奏会や展覧会、ワークショップを見つけたら、アートを通して自分とは異なる感覚や感性に出会ってみませんか。